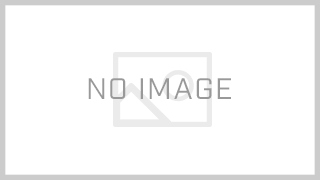みなさんは棋譜並べは好きですか?
棋譜ならべをすると次のような効果があると言われています。
- 布石の感覚が身に付く
- 最新の戦術を学べる
- プロの打ち方を研究できる
囲碁教室の先生は棋譜ならべをしなさいと言いますが
どのように棋譜ならべをするのが効果的なのでしょうか?
棋譜ならべには詰碁では得られない情報が詰まっています。
僕も棋譜ならべは大好きで、今回紹介する方法をずっと続けてきました。
このページでは級位者さんからアマ高段者までに効果的な棋譜ならべの方法を紹介します
このページは、より棋力向上に貢献する方法を紹介しています。
趣味で囲碁を楽しむうえでは、棋譜ならべは好きな方法でお楽しみいただいて構いません。
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
目次
効果的な棋譜並べの方法
棋譜ならべには2つの方法があります。
1つ目は、並べながらじっくり考える方法
2つ目は、さっと並べて手順を覚える方法
あなたはどちらの方法が好きですか?
棋譜を並べながらじっくり碁の展開を考える方法
古くからよく言われる棋譜ならべの方法です。
棋譜を並べながらその棋士になり切り、プロの考え方を脳に沁み込ませることを狙っていると言われています。
結論から言うと並べながらじっくり考える方法はおすすめしません。
その理由を順にご紹介します。
考えるためには基礎知識が必要
全ての段階において言えます。
囲碁は考えるゲームですが、考えるための基礎知識がない状態で考えても答えは出せません。
棋譜ならべで考えるよりは、布石の基礎知識を覚える方が効率的なのです。
たとえば、

この定石で
1図
2図
この2つの図がどう違うか?
なぜ1図は失敗で2図が正解なのか?
これらの答えを考えて導き出すのはプロがやることです。
そして、考えて正しい答えを出せる人には効果的な勉強法です。
この本めっちゃおすすめ。
さっと碁盤に並べて棋譜の手順を覚える
これがおすすめの棋譜ならべの勉強方法です。
棋譜を並べるだけでは勉強にならないという方がいますが、僕はそれは間違っていると思います。
棋譜を考えても答えが出せない以上、考えて感覚を養おうというのは非効率すぎます。それよりはある程度、布石の型を覚えて詰碁に力を入れる方が棋力は伸びます。
さっと並べるという方法は曖昧なので、ポイントを以下にまとめます。
- 1手1手を考えすぎずにささっと並べていく
- 序盤(最初の戦いが起こる直前まで)だけでも覚える
- 気になる部分があればしっかり考えるor先生に聞く
- たくさんの種類の棋譜に触れる
- 本の解説文は読んでも読まなくても良い
この方法が最も棋力向上に結び付く棋譜並べの方法です。
特に③については、気になる箇所ができた時点で布石の感覚ができています。
正しいか正しくないかは置いておいて。。。
自分の中で一定の基準があると、それに沿わない手は『気になる手』になります。
たくさんの棋譜に触れると、この基準が生まれます。
どうしてもわからないという人は、友達と一緒に棋譜ならべをするのもOKです。
僕の場合は覚えた棋譜を友達に見せてあげて、検討することもありました。
一人で並べるより楽しいし、違った視点に触れることができます。
このような手段を紹介するのは、最優先は詰碁だと考えているためです。
布石は型を覚え、中盤、終盤を大きなミスなく打ち切ることができることが大切です。
並べる棋譜についても様々な意見がありますが、僕はどの棋譜を並べても良いと思います。
もちろんおすすめはありますが、興味のある棋士の棋譜を並べる方がモチベーションにもつながり、吸収しやすくなります。
お気に入りの棋士を見つけて、棋譜ならべを楽しみながら強くなれると最高ですね。
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
棋譜並べするために必要な準備
棋譜並べをする時は、ネットで棋譜を見たり、本を読んだりしますよね。
インターネットでは無料で棋譜が観れる場所がありますが、基本的に解説がありません。
「囲碁無料おすすめゲーム、ネット碁サイトを本気でまとめてみた」で紹介したサイトの一部では、リアルタイム中継で解説が入ったりするのでおすすめです。
棋譜並べで役立つ本を選ぶ時には以下のポイントがあります。
- 古い碁なのか?最新の碁なのか?
- 序盤が勉強したい?寄席が勉強したい?
- 好きな棋士がいる?
棋譜並べの目的を見つける
棋譜並べはプロの感覚が身につくと言われますが、具体的には序盤とヨセの勉強がおすすめです。
序盤に関しては「絶対に読むべきおすすめ囲碁本・棋書」で紹介した本が特によくて、序盤の基本的な考え方がわかります。
寄席が勉強したい人は、知得さんがおすすめです。棋譜並べからヨセをどう勉強するのかも書いているので、「江戸時代に活躍したおすすめ囲碁棋士!【本格的に強くなるには】」を読んでみてくださいね。
囲碁が強い人は寄席が強いと言われます。ヨセに自信があれば序盤で焦る必要がなくなり、より地に足がついた打ち方ができるようになり、碁が安定します。
この考え方はすごく大事なので、「囲碁が強い人の特徴から考える上達のコツ【どのような工夫があるの?】」を読んで確認してくださいね。
棋譜並べに必要な道具
棋譜並べに必要な道具は碁盤と碁石ですね。
何を当たり前なと思われるかもしれませんが、みなさんのご自宅の環境に合わせた碁盤の選び方があります。
特にマンションの人は音が響きにくい碁盤が良いですよね。
このように日常的に使いやすい碁盤は安いので、一つ持っておくと時間を気にせず囲碁の勉強ができるようになります。
>>>詳しくわかる!おすすめ碁盤の選び方【囲碁初心者でも大丈夫】
囲碁の上達に棋譜並べは必要?
結論から言うと、棋譜並べは優先度としては高くありません。
棋譜並べは強い人の感覚を学ぶための勉強なので、自分の力が強くなって固定した序盤を決めれば、その感覚に頼らずも勝つことができるからです。
とはいえ棋譜並べで強い人の感覚を学ぶことは、実戦での直感や発想力が飛躍的に向上することでより良い手がてる可能性が上がります。「囲碁上達の方法とは?~初心者から県代表までの道のりを全て公開~」で書いたように、僕も低段時代は棋譜並べにハマりました。
僕は張栩さんの大ファンで、張栩さんの棋譜だけをひたすら並べていました。
こんな感じでやっていると打ち方が似てきたかはさておき、棋力は一気に伸びました。
棋譜並べって不思議ですよね。
1000年も前に打たれた対局でも、全く同じ手順を再現し、ほぼ同じような感覚を味わうことができます。
これは時間を超えて囲碁ファンが同じ趣味を楽しめる、とても魅力的なツールだといえますね。
棋譜並べは効果的な囲碁の勉強であると同時に、とても楽しい囲碁の醍醐味でもあるので、みなさんもぜひたくさんやってみてくださいね。
- 考え込まない
- 量をこなす
- 序盤だけでも覚える
- 好きな棋士に特化する
\完全無料!毎日1問詰碁配信/