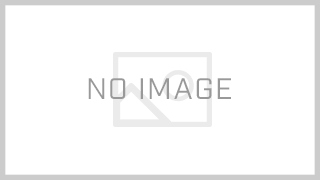囲碁の本でナラビをしっかり解説しているものって少ないですよね。
ナラビというのは、文字通り

並んだ形のことです。
この形の利点は
相手からの利きが少ないこと。
欠点は
足が遅いことです。
さらっと書きましたが、使いこなすのは大変です。
では、実践でのナラビを見ていきましょう。
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
目次
囲碁の必殺手筋、並び(ナラビ)を研究してみた
囲碁ではナラビの手筋が使える場面、使えない場面があります。
並び(ナラビ)を使える場面で打つと、この上ない興趣になる一方で、並びが失敗の局面で打つと廃嫡になりかねない手です。
まずはいろんな実戦を踏まえて、並びの使い方をマスターしましょう!
打ち込みに対してのナラビ

黒は右辺に模様があり、白が1と打ち込んだ場面。
これはよく本にも出てきますね。
ここでナラビが冷静な一手です。
ここでのナラビの意味は
白にサバキの調子を与えないことです。
調子を与えないというのは
様々な利きを見たサバキを防ぐ
つまり、相手のサバキの手段を制限するということです
これによって黒の攻めにより威力が増し
白はサバキに苦労するということになります。
もし、一気に攻めていくと・・・・・
白はこのようにさばいていきます。
白の主張は、あとから

この狙いがあって眼形が厚いということです。
ナラビならこの狙いはないですね。
実戦の進行はこちらです。
白のオオケイマはなかなか面白い手ですが
黒の攻めがうまく決まりました。
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
並び(ナラビ)を使った手厚い守り方

右下はオオケイマカカリからの定石です。
黒は手抜きが多く
その場合に白はナラビが形です。
ここでのナラビの意味は
黒からの利きを消し、中央の勢力を意識したことです。
同時に左側からの利きもないため
打ち込んだ黒に対して強い態度で攻めることができます。
地だけを考えると

トビが良さそうですが
黒からノゾキ利いたり
11-17がうるさかったりと
白としてもデメリットが大きいのです。
並び(ナラビ)で相手の弱点をにらむ

黒は手抜くと死んでしまいますから
何か守らなければいけません。
ここでナラビがいい手でした。
ここでのナラビの意味は
自分の生きを確保しつつ相手の傷を狙うことです。
白は2と守りましたが
黒は先手で生きることができて満足です。
実戦の進行はこちらです。
以下略黒9目半勝ち
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
並び(ナラビ)で反撃する

白が右下をすべってきたところです。
何か受けるかと思いきや、1のナラビが急所でした。
もし白がスミに打つと・・・
白には目がなく、黒はしっかりした形ですので
白は大変ですね。
序盤ながら黒優勢です。
ハネダシに対しては
先手で中央が厚くなり黒大満足です。
ちなみに、すべりに受けると
白の形には弾力がありますね。
簡単に生きています。
この白4のところを黒石に置き換えてみてください。
景色が一変するはずです。
これが急所の見極め方です。
並び(ナラビ)が急所

左辺黒のサバキが焦点ですね。
ここで、白1がいい手でした。
ここでのナラビの意味は
相手のサバキ筋を奪ったことです。
白は勢い良く攻めたいですが

このツケギリが手筋で、簡単にさばいてしまいます。
これを打たせない、ナラビが急所の一手でした。
実戦の進行はこちら
根拠を奪ったあとのボウシには威力がありますね。
黒は苦しい形です。
では、ナラビが失敗する例も見てみましょう
\完全無料!毎日1問詰碁配信/
並び(ナラビ)の失敗図
並び(ナラビ)の失敗(1)開くべきところ

さすがに常識?
これはだめですよね。
1では白は根拠がありません。
黒2と詰められて、一気に苦しくなります。
並び(ナラビ)の失敗(2)勢いが大事なところ

この場合、ナラビには迫力がありません。
黒にボウシされ、黒の勢いが優ります。
このように、ナラビは急所で使うことによって
局面を一気に有利に導くだけの力があります。
以上、「囲碁の必殺手筋、並び(ナラビ)を研究してみた」でした!
\完全無料!毎日1問詰碁配信/